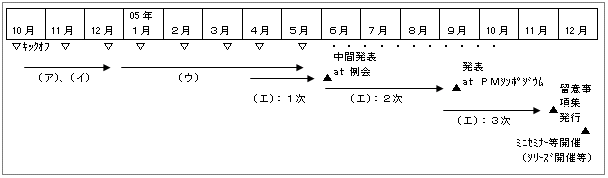IT−SIGは、IT分野に関わりのある企業、組織に共通なPMにかかわる問題、課題を取り上げて、広く社会に提言し解決して、IT産業の発展に貢献していこうという強い意志を持ったメンバーが発起人となって立ち上げ、実質的な研究活動を行っています。
2003年度は3つのWGで活動してきました。
WGの活動の成果については、既に5月の例会で発表いたしましたが、今回さらに9月2日のPMシンポジウムで広く社会に発表・提言いたします。このシンポジウムでの発表を一つの区切りとして、3つのWGは下記のように展開または終了の予定です。
- RFPベンチマークWG:成果をレポート(冊子)にまとめ、経産省、JUAS、JISAなど含め公にアピールし普及させる。
- PMナレッジWG:発表を区切りに活動を終了する。
- PS&HM−WG:活動を継続拡大する。
2004年度は、次の4つのWGを中心に研究活動を行います。これら4つのWG活動に関心をもたれる方々に広く参加していただきたいので、WGメンバーを募集しています。
WGのねらい、活動の進め方、参加要件、スジュール、参加申し込み先等については、各WGのメンバー募集要綱をご参照ください。
- リスクマネジントのポイント整理 WG
実践的なリスクマネジメントのポイントを、よりわかり易く・使い易く整理し、実際の場で役立たせるようにする。
- コミュニケーション・プロトコル WG
RFP、納入ドキュメント、運転説明書などさまざまなドキュメントや、メール、会話でのコミュニケーションなどで、正しく伝わらないことが多いが、その回避策を研究する。
- EVM適用検討 WG
EVMを導入してプロジェクト状況をマクロに,かつ定量的に評価して、プロジェクトの重大問題を見逃さないための一助となる手法を開発する。
- パートナ満足と人材活用(PS&HM)WG(継続)
プロジェクトメンバーが気持ちよく働けるプロジェクト、リーダシップスタイル、チームビルディング、メンタル問題などモチベーションに関連するテーマで活動。
◆申し込み先 : 各WGのリーダ
◆申し込み期限 : 2004年9月30日(木)
《《《 IT−SIGに関するお問合先 》》》 富士通(株) 久保野 邦子
kubono.kuniko@jp.fujitsu.com
- ◆テーマと趣旨:
-
| ・ | 「リスクマネジメントのポイント整理」 |
| ・ | 近年のIT系ソリューションプロジェクトは"短納期・低コスト"の条件下、リスクマネジメントの重要性が益々高まって来ている。
リスクマネジメントに関する論文・記事・書籍 等はこれ迄も種々出されて来てはいるが、上記の動向を踏まえ、実践的なポイントをよりわかり易く・使い易く整理し、実際の場で役立たせるようにしたい。 |
|
- <具体的な項目例>
- :契約形態の選択、顧客/ベンダー各々の果たすべき役割/責任に関する合意、RFP/仕様の扱い、未確定仕様/仕様変更に関する対処、未成熟・未検証技術/プロダクトへの対応、委託管理、適切なプロジェクトマネジャーのアサイン その他。(JPMFジャーナル直近号(2004/7)"ソリューション型PM事例特集"「ITソリューションのプロジェクトマネジメントの特徴と課題」 15頁 表5 リスク要因例 - リスク事項例 を参照下さい)
|
- ◆アウトプット:
-
・リスクマネジメントに関する留意事項集/ポイント集。
・それを使ったミニセミナー等。
- ◆アプローチ方法/進め方:
-
| ・ | リスクと考えられる項目毎に、メンバーの経験/ノウハウをベースに議論を行いポイントを整理。
(とりあえずこのように仮置き。より良い方法/進め方がないかどうかについては最初に議論を行う予定) |
| ・ | 会合は月1回程度(メンバー有志の提供場所にて。18時半〜20時半 等)。 |
- ◆スケジュール:
-
(ア)目的とアウトプットについての確認/議論
(イ)アプローチ方法/進め方 についての確認/議論
(ウ)実際の中身の議論/検討
(エ)アウトプットのまとめ/整理
<スケジュール案> (▽:会合)
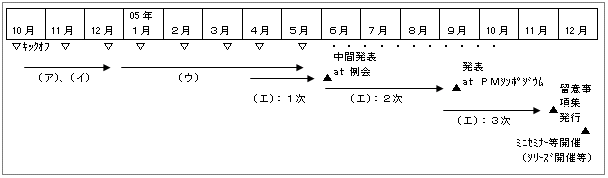
- ◆参加要件:
- IT系プロジェクトのリスクマネジメントに興味/熱意をお持ちの方、経験/知見/ノウハウ等をお持ちの方 等。
《《《 連絡・問合せ先 》》》 新日鉄ソリューションズ(株) 技術部 浅田 誠
asada.makoto@ns-sol.co.jp
- ◆テーマ:
- コンピュータシステム開発では、RFPから納入ドキュメントや運転説明書の類まで様々なドキュメントが作られる。また、メールや会話がでコミュニケーションが行われる。これらのコミュニケーションの結果がコンピュータシステムの形になっていくわけである。その過程で、要求や仕様が分かっていなかった、あるいは、伝わらなかった、誤解したということがしばしば起きる。この様な齟齬をどうすれば回避できるだろうか対策を考えたい。
人の頭の中にあるものは、おそらく言葉に近い形で存在していると思われる。脳の中にあるものを他の人が分かるように出力できれば、問題は減るはずである。つまり、「対象を正しくつかみ」、「話しあるいは書かれた言葉で伝えられる事」が課題である。
わたしたちは、高度で文学的表現を解釈することの訓練は、小学校以来受けてきた。しかし、正確に通じる話や文章を作る技術は教わったことがない。また、あまり分かっていない。
すでに、日科技連でインド、中国、韓国の人と、オフショア開発での、この問題の検討を始めている。この研究を、JPMFと共同で進めることで、より充実した解が見つかると考えている。
また、物事を正しくつかみ表現することができると、国内のシステム開発での問題も減ることが予想される。多くの人々と問題を共有し解を見つけたいと考えている。
- ◆目標:
- (1) 対象の理解の仕方と、通じる日本語の書き方の原則を見つけ整理する。
(2) 誤解を生む表現をしない原則を見つけ整理する。
- ◆進め方:
- (1) 日科技連でので今までの成果を共有(チュートリアル)し、問題を共有する。
(2) 事例および文献から原則を充実させる。
- ◆予定する成果物:
- 下記の項目を明らかにして、ドキュメントにまとめ発表する。
(1) 問題のとらえ方の原則。
(2) 文章の書き方の原則
(3) その背景となる文化
この先に、教材の作成、書籍の執筆、セミナーも視野にいれる。
- ◆参加要件:
- (1) オフショア開発で課題を持っている方、改善しようとしている方
(2) 日本語表現を改善したい方、日本語表現に興味をもつ方
(3) コミュニケーションの問題に興味を持っている方
- ◆スケジュール (案):
- (1) 2004年9月〜 問題意識の共有、チュートリアル
(2) 2004年12月 日科技連「ソフトウェア生産における品質管理シンポジウム」で発表
(3) 2004年11月〜2005年6月 検討・深堀
(4) 2005年8月 まとめ・発表
《《《 連絡・問合せ先 》》》 (株)セゾン情報システムズ 板倉 稔
itakurami@nifty.com
- ◆テーマ:
- プロジェクトマクロ評価におけるEVM適用
- ◆背景:
- リスク評価やプロジェクトアセスメント等により問題プロジェクトの早期検出の努力がなされてきておりある程度の成果も出ている。しかし、プロジェクトの問題の重大さが経営幹部にとって分かりにくく、大胆な対策がなかなか採られないため、結果的に手遅れになるケースもままある。
そこでEVMを導入してプロジェクト状況をマクロにかつ定量的に評価し、重大問題を見逃さないための一助となる手法を開発する。
- ◆主な検討事項:
-
| (1) | 目的
「プロジェクトの進捗状況と費用見通しをマクロに定量評価」することにより、問題プロジェクトの早期検出を図る。つまりPMO等がプロジェクトを監視しエスカレーションするための情報を提供することを目的とする。
(注)EVMはプロジェクトマネジャーがプロジェクト状況を詳細分析し対策を講じるためのツールとしても使用できるが、ここではそれは目的としない。
|
| (2) | 費用/進捗の評価単位をどうするか。
|
| (3) | PVを設定、EV/ACを測定、評価する対象作業を何にするか。
(プロジェクト全体を評価できる代表作業の選定)
|
| (4) | PVの設定、EV/ACの測定の具体的な方法。
|
| (5) | 必要なツール機能、試行 |
- ◆参加要件:
- ・プロジェクトアセスメントにおける進捗の定量評価に関心のある方
- ◆スケジュール:
- ・2005年6月まで、検討、試行、報告書作成
《《《 連絡・問合せ先 》》》 富士通(株) 梅村 良
umemura.makoto@jp.fujitsu.com
- ◆目的(趣旨):
- 詳細で立派なWBSによる計画も、実行出来ないことには意味がありません。
実行するのは、さまざまな組織から集まったプロジェクトメンバです。
指示命令スタイルで、WBSを実現できるでしょうか?
人を動かすには、動機づけが必要です。メンバが仕事意欲を失うとプロジェクトの生産性は極度に低下します。
気持ち良く働けるプロジェクト、リーダーシップスタイル、チームビルディング、メンタル問題など、モティベーションに関連するテーマを扱います。
- ◆進め方:
- このWGは、日科技連とジョイント運用を行います。
3回は、昨年度メンバーを中心に関連知識のレクチャーを行います。
後半は、テーマ別にグループを集い成果をまとめます。
- ◆成果物:
- サブグループに分けて、サーベイ論文、提案書、論文などにまとめ発表する。JPMF、日科技連、PM学会など
- ◆参加要件:
- モティベーション問題に興味を持っていること。
打ち合わせに参加できること。
- ◆スケジュール:
- 調整中 10月から月1回 14時−17時
《《 関連 》》
http://www.debugeng.com/PS/PSWG/PS&HMG.htm
《《 連絡・問合せ先 》》 東京理科大学講師/デバッグ工学研究所 松尾谷 徹
matsuodani@mue.biglobe.ne.jp
▲TOP